まず、俯瞰(ふかん)した山をイメージせよ
ほんと、書くのが苦手❗っていう人にとって、高校受験や大学受験、はたまた就職にまで直面する「小論文」。
小学生までは、「感想文」だったのに、いきなり「論文」とかでてきて、難しさのレベルがあがり、プレッシャーに感じることもあるでしょう。
学校で明確に論文について書き方を習うわけじゃないし、塾によって教え方もさまざまで、どれが正解なのかわからない…。
そんな不安さえ覚える「小論文」ですが、実際どのように書いていけばよいのでしょうか。
なぜ小論文を出題するか?
そもそも、なぜ「小論文」が出題されるか?というところから考えてみましょう。
算数や数学は、計算をして答えを導きだし、答えがあっているかが採点になりますよね。
漢字の問題も、「合っているか」が、正解不正解になる形の問題。

しかし、「小論文」は、この正解を求めて出題されて「いない」のです。それは、「考え方を伝える」ことができるか?を試す科目であり、[客観的」な立場で考えを整理したり、「第三者」の立場で物事に向き合う視点が持てるか? 試されているのです。これが俗にいう「論理的思考」というやつなのです。
論理的思考は、「登山」に例えよう
では、そんな「論理的思考」はどうやって考えていけばよいのか。それは、「登山」に例えて立場の違いを整理していけばよいのです。

山に登るとき、頂上にいくためのルートは様々ありますよね?これが、「考え方」や「立場」の違いであり、どのルートを使って頂上(目指すべき未来や幸せ)に向かってもいいのですが、途中、登り方がきつくて断念せざるを得ないルートがあったり、道がなくなってしまったり、頂上にいけないルートもあるわけです。
こうしたルート(立場)の違いによって、頂上にいけるか、行けないかを記すのが「論文」というわけです。
まとめるとつぎのようになります。
- 頂上→目標や幸せ、解決すべき未来
- ルート→立場や考え方の違い
- ルートの障害→課題や問題
これらにそって、例えば「地球温暖化」について論述しなさい、という問題があったときには、
- 頂上→地球温暖化を解決する
- Aルート→CO2を削減しよう
- Aルートの障害
- 化石燃料に頼る火力発電をいきなり、止められない
- 人間が経済活動を止めるわけにはいかない
- Aルートの障害
- Bルート→CO2を分解する木を植えよう
- Bルートの障害
- 植えても効果が出るまで時間がかかる
- 世界で見れば、どんどん砂漠化している
- Bルートの障害
- 頂上へのルート選択(解決策)
- 削減ペースは落ちるかもしれないが、Aルートが現実的な道だが、加速させる技術開発や、植林の可能性もあきらめない考え方を持つべき
こういう感じで、整理していけばよいでしょう。立場は違えど、頂上にいく(課題を解決したい)という目指すべき地点は同じであり、そこに向かうためにどのルートかよいか、「あなたなりに、他人が理解できる説明で」書く文章が、「論文」ということなのです。
だから、書く前に山を俯瞰(ふかん)でみて、頂上はなにで、ルート(考え方)としてどのような立場が考えられるか、まず整理してからでなければ、「論理的文章」はかけないのです。
ゆえに、小論文は、考え方の違いより、論理的か否かで、満点にもゼロ点にもなる科目。一度身につければ、高得点が狙える科目なのです。

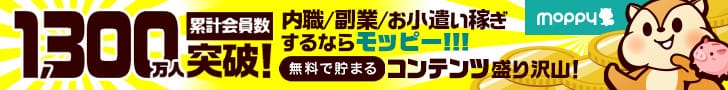



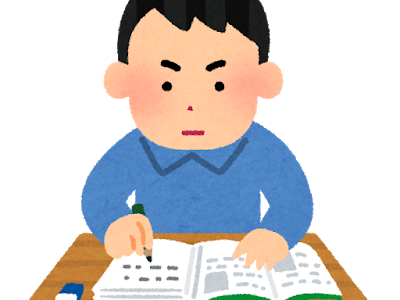



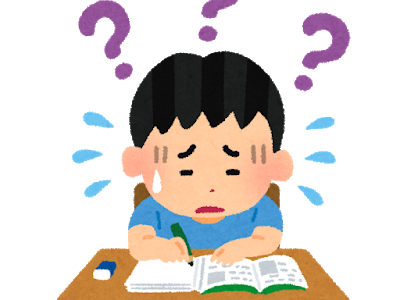


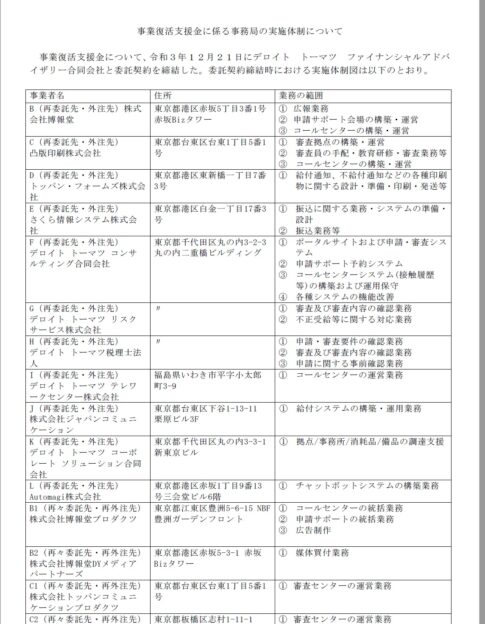

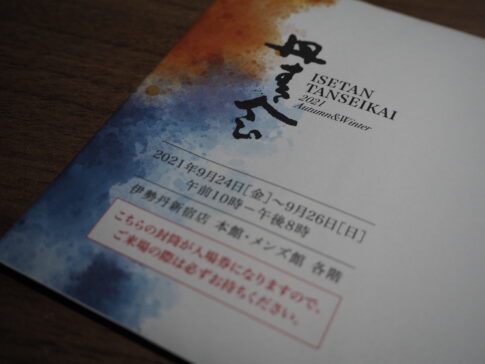
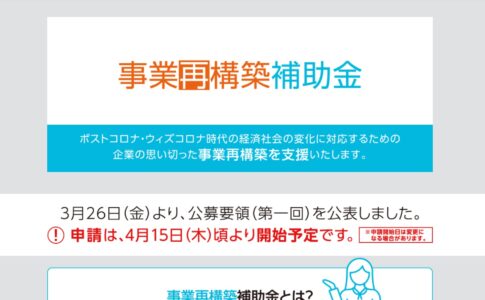
コメントを残す