「加点」より「減点対策」のほうが大事
受験シーズン真っ只中。新しい年を迎えて、今年の入試への思いをあらたにした人も多いかと思います。そんな試験直前対策として、やるべきことを今回はお話しようと思います。
小論文で最も怖いのは、「点数を取る」よりも「減点される」方だと思います。採点を年間6,000枚やってきた立場からすれば、「加点」よりも「減点」で勝敗が決まると言っても過言ではありません。
というのも、考え方は人それぞれ。入試における小論文は「客観的な論述ができるか」にかかっているので、「加点」要素よりも「減点」要素で差がつくと言っても過言ではないのです。
採点する側も、2つの観点から「減点」箇所があるかを見ています。
①論理的な「構成」に不備がないか(例:論理の飛躍)
②考え方に無理がないか(例:誰かが解決してくれる、未来に期待したい)
論理的な文章の進み方は、対策によっていかようにもできます。
特に一番多いミスは「主述不一致」です。主語と述語が違っているということです。
例えば、
[私の主張] 私は太陽光発電はエネルギー効率の点から反対です。
[環境保護派]環境団体の代表は、太陽光エネルギーは自然エネルギーという点で賛成です。
これを1つの文章にする際に、
× 私は、自然エネルギーという点で太陽光エネルギーに賛成する環境団体に反対します。
主述不一致の例
前段の段落で、「太陽エネルギー▶反対」だったものが、2つの文章を合算して「環境団体▶反対」にすり替わってしまうという例。
文章を1つにすることによって、構造が複雑化してしまうので、起こりやすい問題です。頭の中で文章全体の構造と論理的なつながりが記憶できているならばよいのですが、試験本番での緊張もあって、頭の中が真っ白になってしまっては、こうしたミスも起こりがち。
一番の対策は「1つの文には主述は1つ」にするということ。
ちょっと細切れかなと思いながらも、「論理的なズレ」が生じるリスクよりも、シンプルな方が失敗は少ない。リスク軽減という点では、有効な対策といえるでしょう。
「解決策」よりも「選択肢」の整理を
せっかく論述するのであれば、問題解決の糸口なり道筋をつけたい。そう思う受験生も多くいると思います。ただ、小論文で出てくる課題はどれも社会的に長年懸念されていることや、解決策がいまだはっきりしていないものばかり。
人口減少、少子高齢化、地球温暖化、環境破壊、働き方改革、自殺防止、若者雇用など、簡単ではないテーマが並びます。
したがって、「解決策」の提示や提案を無理に行うことよりも、今できることに徹して論述するのが得策。どのような「選択肢」があるのか、という点をまとめるだけでも、論述としてはマルですし、いや二重丸です。
やってはいけない結論のパターン
- 政府・会社が責任を持つべきだ(=責任転嫁)
- 未来の世代に期待したい(=先送り)
- 誰も解決できない(=放棄)
- いまさらどうにもできない(=諦め)
なんのために、論述しているのかわからない結論は、読み手(採点する側)をがっかりさせます。何もノーベル賞を取るような飛び抜けた才能や発想を求めているのでは有りません。受験する世代に無理のない範囲で、「課題解決のスタート地点につけるか」を見ているのです。
評価される結論パターン
- 政治と経済を分けて考えるべき(=問題の細分化)
- 自分だけ好き勝手していたら、友達も失う(=身近な例示)
- 日本も他国並みの投資が必要(=類似)
高い評価を得ようとして、論理に矛盾が生まれたり、主張が飛躍しすぎていたり、目立つことが減点対象となるのが小論文の怖いところ。奇をてらうことよい、「失敗しないこと」を前提に試験に挑むようにしましょう。
そして、いちばん大切なのは「課題文」を正しく読み、理解することです。問題や課題にそってm聞かれていることに答えるのは大前提。課題として出された文章や絵、グラフは必ず大事なところは線を引くなり、マルをつけるなりして、正しい理解を心がけましょう。
小論文攻略は怖くない!
直前で焦りや不安もあることと思います。小論文自体、雲をつかむような試験にみえることもあるでしょう。
でも、この科目は、「考え方の中身」よりも、[考え方の客観性]を持っているかを問われる科目です。だからこそ、
- 問題文を正しく理解しているか?
- 自分の立場と、他者の意見を分けているか
- 意見や立場に客観的な説明があるか
- 字数に収まっているか
が大事なポイント。外さない‼️失敗しないことに注意をすれば、あなたは、合格者に残れる‼️
さあ、直前ですが、落ち着いて試験に挑みましょう‼️

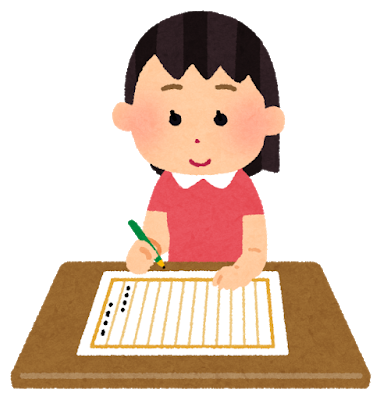
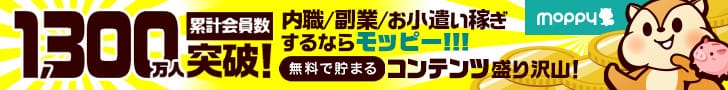





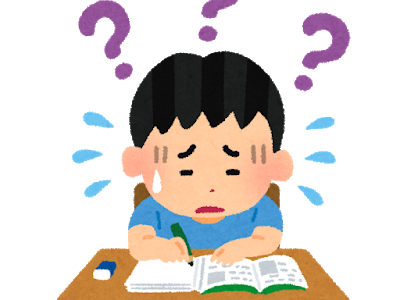
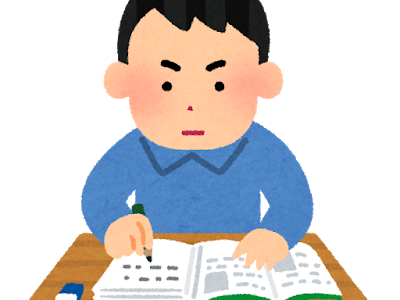



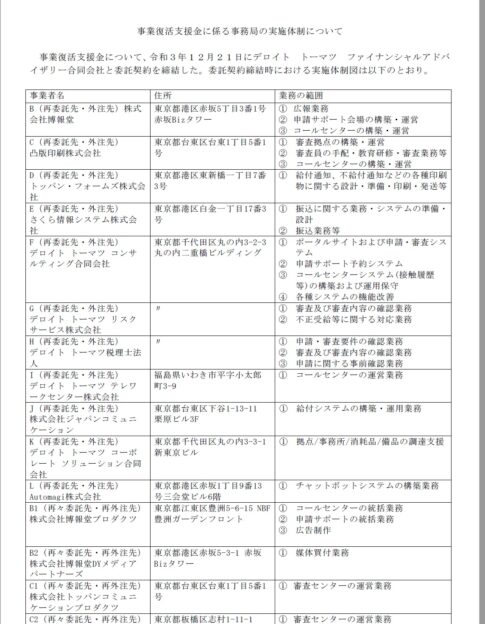

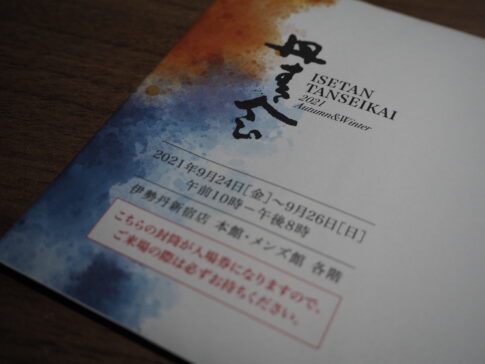
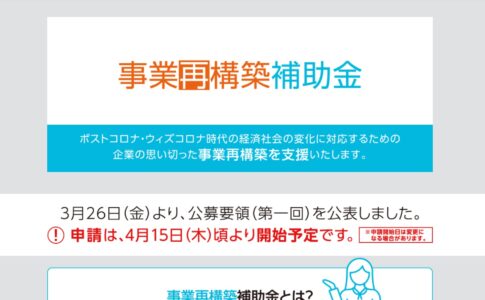
コメントを残す